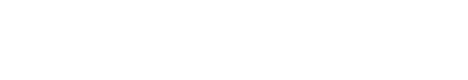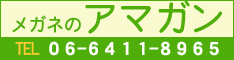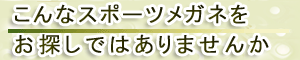目の錯覚
人は情報の80%を「眼」から得ると言われながらスポーツ現場での「眼」への関心は低い。

Q2 正三角形を囲む3種類の線分ab・cd・efではどれが一番長いですか?

Q3 内側にある黒い正方形(右)と白い正方形(左)はどちらが大きく見えますか?
Q1 それぞれの2つの図形は等しくないように思われますが、実際には2つの図形はピッタリと重なります。
Q2 abが一番短くcdが一番長く感じられますが、実際は3つの線分は同じ長さです。
Q3 白い正方形(左)は黒い正方形(右)より大きく見えますが、実際は同じ大きさです。
Q4 acの方が長く見えますが、実際は同じ距離です。
上記から判るように、人間の眼は「見た物」を確実に間違いなく認識できるかどうかはとても疑問ななるところです。スポーツにおいてこの眼の錯覚は競技の勝敗や、記録にとても影響を及ぼすことがあります。これがスポーツビジョンというスポーツと視機能との関連です。
アメリカでは、約50年ほど前からスポーツと機能に関する調査・研究がおこなわれているが、スポーツ選手の視機能の検査、矯正、トレーニングなどを体系的におこなおうという試みが始まったのは十数年前からである。アメリカではこれを「スポーツビジョン」と総称している。スポーツビジョンを目的として、アメリカ・オプトメトリック協会のなかに「スポーツビジョン・セクション」が1978年に設立された。その後、1984年にもう1つの組織である「ナショナル・アカデミー・オブスポーツビジョン」がつくられている。いずれの組織も、眼科医、オプトメトリスト、研究者、コーチなどからなっている。
アメリカには眼に関する専門家として、オフサロモノジスト(眼科医)、オプトメトリスト(検眼医)、オプティシャン(眼鏡士)の三業種がある。オプトメトリストは、わが国ではこれに相当する制度はないが、眼科医と眼鏡士の中間に位置し、視力の検査、視力障害を改善する処方や視力訓練などを業務としている。わが国でも屈折検査は本来、眼科医の仕事であるが、実際には眼鏡店でもおこなわれているように、アメリカでもオプトメトリストと眼科医の境界はあいまいで一部ではだぶっているという。オプトメトリストの作成した処方で、オプティシャンといわれる技師が眼鏡をつくることが多いという。
1990年「ナショナル・アカデミー・オブ。スポーツビジョン」の総会では、スポーツと視機能の基礎的な研究の発表、スポーツ選手用のコンタクトレンズの開発、スポーツ中の眼傷害の報告などが中心であった。プロスポーツと契約して選手の視力矯正や視機能のトレーニングをおこなっているオプトメトリストの実践報告もあって内容は多彩であった。視機能をトレーニングするというコンセプトはアメリカでも目新しいようで、トレーニングの実践コーナーでは参加者との間で活発な意見交換がおこなわれていた、
アメリカのスポーツビジョンの概念は、主として次の4つである。
・検査
・矯正
・強化
・保護
スポーツにおいて必要な視機能を検査し、矯正できるものは矯正し、視機能を強化し、スポーツ中のケガから眼を保護するといういもので、基本的には選手のもpつポテンシャル(潜在能力)を向上させ、パフォーマンスのアップに寄与しようというものである。アメリカでは、コロラドスプリングスにあるオリンピックトレーニングセンター内にスポーツビジョンセンターが設置され、これまでオリンピック候補選手三千名の視機能が検査されている。
例えば、SPORTS VISION TRAINING より
■スポーツビジョンの広がり
スポーツビジョンが、特定のスポーツ向けの視覚機能を鍛え、高める方向に利用されるようになって、眼のケアの分野において著しい進歩が見られる。何十年もの間、従来のオプトメトリストは選手の視力を測り、メガネレンズを処方した。しかし、この静止視力を測るやり方ではもはや十分とはいえないだりy。筋力と敏捷性を選手の間に浸透させた運動生理学者に遅れること20年、医師は動体視力を初めたくさんのスポーツビジョンの機能を測り始めるだろう。これからも選手は標準的な眼の検査を受け、メガネやコンタクトレンズを使うが、視覚は運動技能向上のための重要な方法としてまったく新しい広がりをもつことになる。スポーツビジョンのコンサルタントが、すでにアドバイスをしているチームもある。フィラデsル・フライヤーズ、アメリカのオリンオイックホッケーチーム、カンザスシティ・ロイヤラズ、ダラス・カーボーイズ、ニューヨーク・ジェッツ、ニューヨーク・レンジャーズなどである。これらのドクターは各選手の視覚機能を測り、その長所、弱点を図に表している。そしてコーチ、選手、トレーナーに弱点を補強する特別プログラムをすすめる。またすでにちからがある機能については、いっそうのレベルアップを図るドリルを用意する。コンサルタントが段階を踏んだプランをつくり、選手がそれによって致命的ともいえる視覚の欠点を克服できた例もある。また、コンサルタントは、チームのスカウト要員としても貴重な存在である。№にをするかと言えば、おもに有望な選手の才能を評価し、その技術ースイード、筋力、敏捷性を見る事である。スポーツビジョンの専門家が招かれ、各選手の視覚面の能力を調べるテストを行うこともある。このテストの結果は、選手選考にひじょうに影響を与えることもありうる。ランニングバックの視覚反応時間、ピッチャーの視覚集中力、外野手の深視力は、将来、選手として成功するかの重要ポイントである。たとえば、同じくらいの力をもったワイドレシーバーがいたとしよう。ともに4.5秒で40ヤードをランするが、2人ともパスをよく落とす。1人はスポーツビジョンに矯正可能な問題をもっており、もう1人は診断では視覚の問題は見つかっていない。もしあなたがスカウトだったら、これだけの情報からどちらの選手をチームにスカウト、kあるいはドラフトするだろうか?スポーツビジョンのコンサルタントなら、おそらく視覚に問題のあるほうの選手を選ぶようにアドバイスするだろう。パスを落とすという欠点も原因がはっきりしていて直せるからである。もしパスターンもうまくスピードもあれば、ドラフトの7巡目で指名される価値はあるだろう。
■スポーツビジョンの成功
今日の運動選手は精神的、身体的な備えは十分である。であれば視覚的にも十分準備されるべきだろう。ロジヤー・バニスターが1マイル4分を切る記憶を出して喝采をうけたのはほんの少し前なのに、いまやこれが平凡な記録になっている。どのスポーツでも記録は次々に塗り替えられていく。これはいまの選手が前より速くうまいためだろうか?それとも記録を破るために必要なものが、細部にわたって時間をかけ細心の注意を払って準備され、詰め込まれているからだりyか? スポーツビジョンのトレーニングを使ってすでに何人かの選手が、ドラマチックな成功を収めている。4度目のスタンレー・カップを獲得したニューヨーク・アイラインダーズ、ビリー・スミスはプレーオフの前に、視覚反応時間と運動視覚追跡能力をあげるためにスポーツビジョンのトレーニング方法を使った。その後彼はファースト・ゴーリーになり、スタンレー・カップのプレーオフでは15勝を記録した。同じくスポーツビジョン・トレーニングを受けたプロテニス選手、ヴァージニア・ウェードは、1977年のウインブルドン決勝でクリス・エバートに勝ったのは眼の専門家のおかげだと考えている。彼女は、「ドクターのおかげで私の反射運動作はスピードアップし、コートでいっそう効果的に動くことができた」と、いう。シャロン・ウォルシュ、バッキー・デント、ジョージ・ブレット、ピート・ピーターも、スポーツビジョン・トレーニングの恩恵に沿している。
注意してほしいこと:30日、いや2年間のスポーツビジョン・トレーニングによっても調整のついていないバスケットボールの選手を、”ドクターJ”こと、ジェリウス・アービングのようには変えることはできない。しかし、スポーツビジョンによって次のような違いは出てくる。試合終了間際まで集中力を維持しているかなくしているかの違い、スピードボールを打つ瞬間までずっと追跡できる人と、8メートルも手前にボールを見失ってしまう人の違いである。スポーツビジョンの分野は、いままさにテクノロジーの援助を求め始めている。スポーツビジョンの専門家の手で考案されたSaccadic Fixator,タキストスコープがロッカールーム、トレーナールームにもある。現代科学の助けを借りた将来のビジョントレーニングは究極の選手を育成する最新の方法を提供するだろう。
永遠のスラッガーであるピート・ローズは、スポーツで最もむずかしい技能ーボールを打つことーをわずかこれだけの言葉にまとめた。いわく「ボールを見て、ボールを打つ」。ローズのこの簡素な言葉がときの試練をへて、いまから25年後も同じように正しいとわかるだろう。しかし、「ボールを見る」というフレーズは新しい、さらに細かい意味合いをもちはずである。そしてその意味はさらに研究された形を変えて、やがて「見る」とは、さまざまな視覚機能が一体となってダイナミックに機能し、選手に抜きん出た力を与えるものと理解されるだろう。
■ナブラチロワのメガネ
ウインブルドンからのテニスのテレビ中継で、ナブラチロワの厳しい表情がズームアップされたとき、彼女のメガネが遠視のように見えた。彼女がメガネを使いだしたのは、現役も終わりごろの数年間ではなかったろうか、縦に結んだ鉢巻きとともに著者には深い印象を残している。彼女の裸眼視力は、長い間裸眼でトッププレーヤーを続けていたことからみて、おそらく1.5程度はあったものと推測される。それでも、120~140㎞のサーブに応じるためには、よりよい視力を求めての、後年の対応ではなかったのだろうか。<安藤 純著>